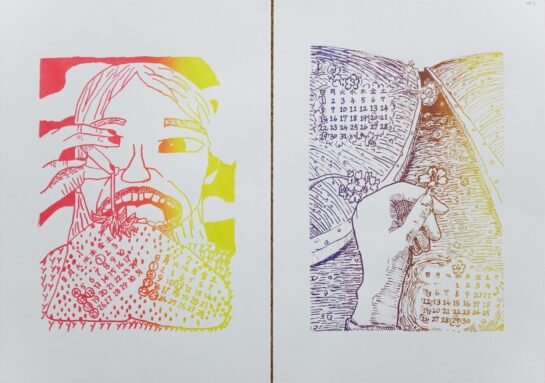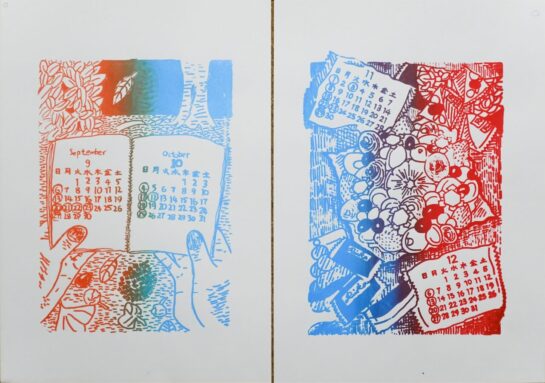午前クラスは今週から新しい課題、年度末恒例の自由制作です!
でも全くの「自由」は実は一番難題💦なので、部屋中央に置かれたアロエを手がかりに発想を広げていきましょう。それでも状況(どこ?時間は?)/物(何と一緒に?)/関係(どう扱う?)の組み合わせで無限に絵の可能性は広がります。今週は目で観察し頭をフル回転でアイデア出し。植物の絵といったら、ジョージア・オキーフが1番に思い出されます。花や描きつつもグッとクローズアップすることでまるで抽象のように見えます。ぜひ知っておくといいですね。
午後クラスは、来週完成ですので、今日はほぼ完成までどんどん描き込んでいきました。地面との接点や、物の位置、形を明確に、鉛筆を少しずつ立ててハッチングで描いていきます。